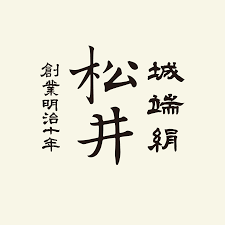Uターンと、蚕との出会い
今のお仕事をはじめたきっかけについて教えてください。
松井さん:私は松井家の三姉妹の三女として生まれました。正直言うと、小さい頃から「継げ」と言われたことは一度もなかったんです。
「女性が家業を継ぐ」っていう発想自体が、当時の私たちのなかにはありませんでした。
大学卒業後は東京で証券会社に就職して、営業職として働いていました。外回りも多くて、街を駆け回っていた毎日。その頃はまさか自分が富山に戻るなんて、想像もしていなかったですね。
転機が訪れたのは2009年の秋。父が東京に来るタイミングで「ちょっと面白い人に会いに行かんか」って誘われたんです。染の研究をしている会社が千駄ヶ谷にあって、そこに一緒に行こうと。仕事中だったので、当時の上司には「チラシ配ってきます!」ってこっそり抜け出して(笑)
そこでの会話が、本当に衝撃的だったんです。父とその会社の社長が、お蚕さんの話を始めて。
「蚕ってちっちゃいのに、“一頭二頭”って数えるんだよ」って言われて
「え?なんで?」って聞いたら「人間と古くから付き合いがあるから」って。
ほかにも、繭が紫外線をカットすること、水分を吸ったり吐いたりする調湿機能があること、皮膚と同じアミノ酸構成だから手術の糸に使えること……聞けば聞くほど驚いて、感動して。
それまでシルクって、「おばさんっぽい」とか「古臭い」っていうイメージしかなかったんです。でも実際は、めちゃくちゃ高機能で、すごい繊維だったんだって、そのとき初めて知ったんですよね。
「これは…やらんと後悔するかもしれん」って、自然と思ったんです。
それが、Uターンのきっかけです。
その年の年末に帰省して、父に「帰ってきてもいい?」って伝えて。年明けに支店長に辞職を申し出たら「せめて3か月いてくれ」って言われて。
そこから3月まで働いて、4月からは簿記とかの勉強を始めて、2010年の8月、正式に松井機業に入社しました。
三姉妹のうち、長女はもう早々に結婚してしまって(笑)
次女は私と東京で2人暮らしをしていたんですが「もう潰れてもいいんじゃない?」くらいのスタンスだった。でも、私はこの魅力的な伝統を残したいと思った。
今では次女(姉)も一緒に仕事をしています。
私が東京で過ごしたのは、ちょうど8年くらい。大学4年と、証券会社での3年、あっという間でした。楽しかったし、友達もいた。
でも、江戸時代と違って、今はどこでもすぐ繋がれる時代なので「会いたくなったらまた来ればいい」と思っていました。
あのとき、千駄ヶ谷で蚕の話を聞いてなかったら、私は多分、今も東京で、マンションかなんか買って、普通に暮らしてたと思います。ほんとに…あそこがターニングポイントでした。

絹と向き合う日々、夫と歩む道
入社してから大変だったことはありますか?
松井さん: 2010年、松井機業に入社してからは、もう現場に飛び込みました。糸繰り、管巻き、整経、製織、精練、染色…そして生地と和紙を貼り合わせる「張り合わせ」まで、一通りぜんぶ。
まずは「どれだけ大変か」を自分で知ることが大事だと思ったんです。
もちろん、すぐに全部ができたわけじゃないし、わからないことだらけ。でも、やってみるとわかるんですよね。この工程は人の手がどうしても必要なんだな、とか、機械化されても“糸と会話する感覚”がないとできないな、とか。
特に、蚕が2頭入った繭は糸に節が出るので、切れやすい。それをつないでいく作業なんて、本当に人の手じゃないとできないし、だからこそ、そこにあたたかみが生まれるんだと思います。
あと、当時感じた一番の課題は「今の時代に合うものを作れていないこと」でした。でも技術はある。
ただ、現代の暮らしにフィットする提案ができていなかった。それに、どこに営業をかけていけばいいのかも、さっぱりわからなくて。販路開拓は、ずっともやもやしていた部分でした。
そんなとき、大きな存在になってくれたのが夫です。
彼はもともと畑をやっていた人で、土壌の健康を調べるようなことをしていました。うちのクワ畑の件で市長から紹介されて出会ったんですが、話してみると「おもろい人やな」って(笑)
結婚してからは機械も直せるし、調べ物もうまいし、営業の戦略も一緒に考えてくれる。機械の不調もどんどん改善してくれて、作業効率も格段に上がりました。
彼のおかげで、私は今、ちゃんと“届けたいところに届ける”営業ができている気がします。まさに二人三脚。すごく、すごく助けられています。
私自身は営業している中で「こんなもん使えん」と言われても「じゃあどうしたら使ってもらえますか?」ってしつこく聞いて(笑)
そして次に活かす。そんなことを地道に繰り返してきました。正直、「しんどい」と思ったことはあまりないんです。むしろ、楽しかった。自分の知らなかった絹の魅力に、改めて毎日出会い直しているような感じです。
この業界は、たしかに“衰退産業”って言われることが多い。でも、私は「朝の来ない夜はない」っていう言葉が好きなんです。
寒い冬にこそ、根っこを深く張る準備をする。そうすれば春が来たときに、きっと花を咲かせられると信じていました。希望を持ち続けて、毎日を生きる。そんな想いで、今も変わらずこの仕事に向き合っています。
エゴから感謝へ、命を受け継ぐものづくり
仕事への想いを教えてください
松井さん:最初は、ほんとにエゴに燃えてたんですよね。
「私の代で花咲かせる!」「東京に支店つくって、海外にも展開して、年商何十億!」みたいなことを本気で思ってました。
自分が、松井機業をなんとかするんやって。そんな気持ちがメラメラしてました。
でも、ある時、その思いがガラッと変わる転機があったんです。
須藤玲子さんっていう有名なテキスタイルデザイナーの方がいて、経営とデザインを両輪で回してる女性が六本木におられるって聞いて。
「一度お会いしてみたい」って思って、紹介のつても待てず、直接電話してアポ取って、そしたら「明日の3時なら空いてる」って言われて、急いで飛行機取って六本木に向かったんですよ。
でも、その日が 3.11 だったんです。
近くの喫茶店でアポの時間を待っていたら、突然、電信柱がグラグラ揺れ始めて。どんどん大きくなる揺れに、さすがに「これは…」と思いました。
それでも、行ったんです。
どうしても、あのアポを逃したくなかった。
“滅多に会えない人に会えるチャンス”が、やっと巡ってきた。
地震が来ようが、ビルが揺れようが、私は、行かなきゃって思ってました。
今思えば、どうかしてるなって思います(笑)
須藤玲子さんは、いまでも私のことを「そんな日に来た子」って覚えていてくださってます。
その時、大量に抱えてきた生地を見せながら「どう思いますか?」って聞いたんですけど、須藤さんは何も言わない。ただ、静かに私を見ていた。怖いくらいに、静かで。
そして最後に、ぽつりとこう言われたんです。
「あなた、布との距離があるわ」
その言葉が、ガツンと胸に突き刺さりました。
私は布のそばにいたつもりだった。でも実際は、自分の欲とか、結果とか「上に行くための手段」としてしか見ていなかった。
布と心が通ってなかった。——そのことに、やっと気づけた瞬間でした。
私がこの家に戻ってくる前に、祖父に「継ぐことにしたよ」と報告したら、意識のほとんどない状態だったのにしっかり目を合わせて頷いてくれて…その1週間後に亡くなったんです。
それ以来、なんだか祖父がそばにいてくれてるような気がして。
だから、須藤さんにお会いした後に亡くなった祖父にもお仏壇の前で相談して。
その時に周りにあるしけ絹の襖を見たらいつもより輝いて見えたんですよね。
それから、もっと身近の状況を見るようになりました。
当時はエゴに燃えて東京にばかり目を向けていたけど、南砺市には、富山には、ものづくりも、自然も、すでにたくさんあるんですよね。

お蚕への感謝と、願い。
それからはどう変化しましたか?
松井さん:それから、お蚕さんの事をもっと知ろうと思って、自分で飼ってみたら、わかってたつもりだったんですけど、もうびっくりするくらい小さな命で。
卵から生まれて、筆でやさしく運ばなきゃいけないくらい繊細で、ほんとに愛着が湧くんです。でも、長い糸を取るには、その子たちをお湯につけなきゃいけない…。
わかっていたけど、実際にやってみると胸が張り裂けそうでした。
そのとき、別院で仏教の話を聞いて、命のこと、自分の力のこと、自然の営みに感謝すること、たくさん考えさせられました。
「生かさせてもらってる」って言葉が、やっと腑に落ちて。
だからこそ、私は「命をいただいてるからには、人間の命にちゃんと役立つものを作ろう」って思うようになりました。
それは、自分たちの利益や、業績という目に見える結果だけに執着するのではなく。
私たちが立ち上げたブランド「JOHANAS(ヨハナス)」では、フェムケアグッズにも取り組んでいます。私自身、生理不順にすごく悩んでいた時期があって、いろんな婦人科にも行ったけど改善せず。
でも、シルクを当てたら調子が良くなったんです。調べたら、奈良時代にはシルクを纏うことが“薬”だったって知って。
「ほんとに体が喜ぶものって、何なんだろう?」
そう考えるようになりました。
最近では、ハーブテントの開発にも取り組んでいます。
お蚕さんを知っていくうちに、循環の美しさにも気づきました。
繭は人間にとっては絹になるけど、お蚕さんにはもう不要なもの。さなぎは魚のエサになって、フンは漢方薬に。
無駄が一切ない。お蚕さん自体がもう、サーキュラーエコノミーの体現者なんです。
だから精練作業も、なるべく自然に戻す方法に変えていきたいと思っていて、最近は稲の茎の灰を使った灰汁精練も始めました。
その排水が川に流れて微生物が増えて…すくなくとも松井機業の周りだけは、なんか自然がめっちゃ元気になったらいいなって思ってます(笑)
エゴに燃えていたあの頃の私から、ずいぶん変わったけれど、いまは「命と向き合いながら、ちゃんと役立つものをつくる」という、当たり前だけど大切なことを胸に、仕事をしています。
シルクに包まれて眠る宿と、“富山県民お蚕三頭飼育計画”
今後の展望について教えてください
松井さん:これからやっていきたいこと、2つあります。
ひとつは「しけ絹の空間に泊まれる宿」をつくること。
うちの絹って、壁紙にもなるんですよ。シルクの壁紙に、シルクのシーツ、シルクのパジャマ、シルクのアイマスク…もう全身でシルクを感じられる空間って、ほんとに気持ちよくて。
シルクって“七次元素材”とも言われていて、愛の波動があるとか、神様に一番近い繊維なんて呼ばれてたりもするんです。
だから、アイマスクもまるで“お母さんに手を添えられてる”ような安心感があって、不安で眠れないときも、気づいたらスッと眠れてたりする。
照明も、しけ絹で包んだライトだと、ほんとに木漏れ日みたいな優しい光になるし、カーテンにしても素敵。その空間で過ごしてもらって「家でも再現したいな」って思ってもらえたら、うちの商品を一式買って帰ってもらえばいいし(笑)
そうやって“体験から広がるブランド”を目指していきたいんです。
もうひとつが富山県民お蚕三頭飼育計画です。(笑)
いま、富山県の人口って100万人切ったくらいなんですけど、実はうちで扱う年間のお蚕さんの数がちょうど300万頭くらいなんですよ。
つまり、県民1人あたり3頭ずつ飼えば、ぴったり使い切れる(笑)
でも、これってただの冗談じゃなくて——
私自身、お蚕さんを飼って初めて気づいたことが、たくさんあったんです。
お金があっても、水や土がなければ生きていけない。農薬がかかるとお蚕さんは死んでしまう。
桑の葉っぱは、農薬がない場所じゃないと育てられない。
つまり、「命にとって本当に大切なものって何か」っていう感覚を、お蚕さんたちが教えてくれたんですよね。
テレビでは豪邸が映し出されたり、野球選手の年俸が何億!とか、そういった意味での“社会的成功”の価値観での話ばっかり。
でも、本当は、私たちはもう、幸せの種を手の中に持って生まれてる。
お蚕さんと向き合う時間が、それを思い出させてくれるんです。
だから、富山県のみんなが3頭ずつでもお蚕さんを飼ってくれたら、きっと、すごく豊かで、優しいエリアになると思うんですよね。
環境的に無理な場所もあるかもしれないけど、小学校の授業でも飼育されてる地域もありますし、絶対に不可能じゃないと思っています。
そして、育ってきたお蚕さんたちは
ふわふわで、真っ白で、まるでうさぎみたいに、かわいいんですよ。
小さな手で「お手」みたいな動きをするんです(笑)
もう、ほんとに愛おしい存在です。
“天の虫”と呼ばれるこの命と、もっと多くの人が向き合ってくれたらいいなって思っています。
自分の感覚を、信じてあげてほしい
最後に、若手世代へのメッセージをお願いします
松井さん:若い頃の私は、世間の目とか、まわりの評価とかばっかり気にして生きてたなって思うんです。そうやって選んだ道は、なんとなく“正解”のように見えても、心はどこか苦しかった。
たぶん、心が薄汚れてしまってたんだと思います。
だから、いま若い人に伝えたいのは
「もっと、自分の感覚を信じてあげてほしい」ってこと。
感覚って、難しいように感じるかもしれないけど、たとえば「今日なに食べたい?」って自分に聞くことからでいいんです。
今、なにが食べたいんやろ?って。それが「自分の感覚を拾う」ってことの第一歩やと思います。
ワクワクすること、胸が高鳴ることって、実は“神様からのヒント”らしいんですよ。
もし人生で迷ったら、「どっちのほうがワクワクする?」って感覚に聞いてみてほしい。
その先に、意外とスムーズに進む道が待ってたりします。
今の私は、「自分でどうにかしなきゃ」っていうよりも、「きっとタイミングが来たら、必要な人が現れる」って信じてます。
まるでRPGみたいに、アイテムを持った人がぽっと現れる(笑)。
神様が「はい、次これだよ」って教えてくれてるんやろなって思うんですよ。
だから——
「考えすぎずに、ちゃんと感じる」ことを、忘れないでいてほしいです。
頭で考えるより、細胞レベルで「気持ちいい」と思えるものに出会ったとき、それはきっと本物。
私は“ヨハナス”っていうブランドを立ち上げて、そういう商品をつくりたいと思ってます。
手に取って「これ、気持ちいいな」「なんか好きやな」って感じてもらえるものを。
それが、きっと日々の暮らしを、そっと豊かにしてくれるから。
自分の内側の声に耳を澄ませて。
それは、いつだって、ちゃんとあなたを導いてくれると思います。
撮影:鷲尾 和彦
ライター:長谷川 泰我