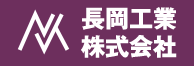社会の“当たり前”を支える、縁の下の二本柱。
事業内容について教えてください。
長岡さん:主にやってるのは大きく分けて2つ「ガスを安全に使えるようにする仕事」と「塗装」です。
ガスの充填容器は法律で数年ごとに検査が必要だと決まってるんです。周期は容器の製造年数によって異なりますが「ちゃんとガスを詰めても安全ですよ」「破裂しませんよ」って確認するための検査です。
容器のサイズも様々で、病院で使うような小さな酸素ボンベから、人が中に入って検査するような20トン、30トンの巨大なものまで。
扱うガスもプロパン、酸素、窒素、水素、アンモニア、塩素と多種多様。富山県内でこういう検査ができる場所って少ないので「これもできんか?」「あれもできんか?」って話がどんどん来るようになって、自然と対応できるガスの種類も増えていった感じですね。
ガスの仕事は急激に増える事はないですが、逆に言えば景気に左右されにくい。リーマンショックが来ようが、天災が起きようが、法律上必ず検査が必要なんです。
もちろん人口減少の影響はありますけど、人口も急激に減るってことはないですし。
塗装業のきっかけは、ガスの容器って金属製なので、どうしても表面が錆びるからです。
だから検査工程では、塗装を剥がして中の地金の状態を確認して、再塗装するって流れがあって。それも法律で決まってる工程なんですけど、そのための塗装設備がうちにある。
じゃあこの塗装設備をもっと活用できんか?ってことで始めたのが今の塗装事業のきっかけでした。
特徴としては「焼き付け塗装」をやってること。
これって簡単に言うと、塗った後に熱をかけて塗料を固める方法で、主に工業製品に使われるんです。バスの部品、建設機械の部品、ガスメーターなんかもそうですね。
全国を走るバスには、うちが塗った部品が必ずどこかに使われてます。
だから、バスが走っとると「あ、今日もうちの仕事が走っとるな」って思うんですよ。
振り返ってみると、ガスの充填や検査も、塗装も、結局は「安全に長く使うため」の仕事なんですよね。どっちも派手じゃないけど、世の中に必要とされとるからこそ続いてる。
そこに誇りを持ってやってます。
「事業撤退したから始めた」請負から始まった企業の根
長岡工業の歴史について教えてください
長岡さん:創業は1963年、昭和38年です。
きっかけは、うちの祖父が当時勤めていた会社の事業が一部撤退することになったっていうのが始まりです。
「まだ仕事は残ってるから、請け負いでやってみれば?」という形でのスタートでした。
つまり、創業社長が「やりたいから始めた」のではなくて「前いた会社が撤退することになったから始まった」っていうのが正直なところです。
最初のうちは、全然仕事がなかったみたいで、ダムの清掃工事やったり、黒部峡谷のトロッコの整備したり、ほんとに目の前の「できそうなこと」は全部やってたって聞いてます。
結果的に残ったのが、いま主力になっているガスの仕事だったというわけですね。
当時はもう、完全に手探り状態でやってたみたいで、2人で3交代制のように回してたそうで。
朝8時から仕事して、8時間寝て、また仕事して、また寝て、みたいな。泊まり込みで、飯食って仕事して、仮眠して、風呂入りに帰って、また弁当持ってきて仕事して……そんな毎日をひたすら続けてたみたいです。
ただ、祖父が元々勤めていたのはそれなりに大きな企業だったんで「人事考課制度」とか「会社の仕組みの作り方」っていうのはすごく参考にしてたようです。
性格的にも細かくて、勉強好きな人だったんで、業務内容は自分で学びながら開拓していったけど、給与計算とか請求書発行とか、人事評価とか、いわゆる会社の“型”みたいな部分は、当時の会社をそのまま参考にして運営してたって話でした。
ちなみに、父が二代目を継いだんですが、もともと上場企業のエンジニアをしていた人で、この会社に入ったときには「これは会社とは呼べない」とは言いながらも、一生懸命、会社としての体裁を整えていってくれた。
どちらかといえば初代のように「攻める」タイプではなくて、内部の整備を重視する人でした。
職場環境の改善だったり、働きやすさを整えたり。
どちらかというと手広く事業展開して急成長を目指すというより、後を継いだ会社を“長く存続させる”ということに重きを置いていたと思います。
会社のスタート地点は本当に「目の前の仕事を全部やる」っていう精神だったし、二代目は自分でゼロからすべて考えるよりも、他社の良い部分を素直に取り入れる柔軟性があった。
それがうちのDNAとして、今も息づいていると感じています。

唯一怒られた日。「作業するためにお前はここにいるんじゃない」
代表就任のエピソードを教えてください。
長岡さん:僕がこの会社に入ったのは2007年、29歳のときでした。富山大学を出て、富山の地銀に勤めて、その後、長岡工業に入ったという流れです。
銀行では、地域の似たような規模の中小企業の社長たちと話す機会がすごく多くて、それが本当にいい勉強になりました。
社長の人となりや、会社の方針、経営判断を直接聞ける環境にいたおかげで「自分だったらこうするな」っていう経営シミュレーションを、ずっと頭の中でできましたね。
しばらくは銀行に勤めてやっていくつもりだったのですが、転機になったのは父の体調不良でした。
ある日突然、心臓を悪くして集中治療室に入って「もう出てこれんかもしれん」と言われて。
その状況を見て、迷わずこの会社に戻る決意をしました。
会社に戻ってきてから、先代から唯一叱られた出来事があって。
新しい工場の立ち上げにあたって、プラントの実験から自分で始めて、データを取って、現場で作業してたんですよ。そしたら父に言われたんです。
「これは新しい仕事のためのデータ取りだと分かっとる。でも、お前がその仕事をいつ、誰に、どうやって引き継ぐつもりなんや? お前は作業をするためにこの会社におるんじゃない。そういう給料は払ってない」と。
仕事のことで怒られたのは、後にも先にもその一度だけ。
でも、あのとき結構ガツンと言われて。
「自分は“経営者”としてここにいるんだ」という立ち位置を改めて自覚しましたね。
もちろん、現場で手を動かすことも大事だし、非常時に動くこともある。
でも、それは“1日で抜けられる”状況でやるもんであって、何日も連続で現場に入ってちゃいかんと。父も、きっと何日か様子を見とったんでしょうね。
「またやっとるな、あいつ」って。
結局、経営者の役割は指揮者と同じであって、自分で演奏してちゃいけないってことだったんですよ。
「ほら!俺のチェロうまいやろ!ヴァイオリンだってほら!」って、自分のやっていることにバイアスが掛かるじゃないですか(笑)
父は求めるべきことは求めるし、でも、それ以上の口出しはしない。2020年に社長を正式に交代したときも「もう十分やったから、あとは任せた」ってスパッと辞めていきました。
その後、父はゴルフ場で倒れて、そのまま亡くなりました。
ゴルフが本当に好きな人で、きっと最後まで「これでよかった」って思ってたんじゃないかな。
いまだに、僕はゴルフ場に行くと父との会話を思い出すんです。
仕事の話はしないけど、いろんなことを話したあの感じが、今でも残ってるんですよね。

「やってみたら?」から始まる、社員と会社の未来設計
仕事への想いを教えてください
長岡さん:会社に対しての想いで言うと、やっぱり「今日より明日、もっと良くしていきたい」って気持ちはずっとあります。
それは会社に限らず、社会全体に対しても同じで「ちゃんと世の中の人たちが幸せになっているかどうか」この会社を通して、何かしらプラスの効果を社会に与えられてるか、そういう視点を持っていたいんです。
もちろん、その中には社員の幸せも含まれています。
うちのメンバーが昨日より今日、今日より明日と、より良い状態でいられるかどうかっていうのは、常に気にかけてますね。
そのためには、新しいことにチャレンジしていかなきゃならんと思ってて。
事業って、新しい何かをやらなければ、どんどん停滞してしまう。株価もそうでしょう。上がったり下がったりはあるけど、大事なのは「トータルで上がってるかどうか」
短期的な下がり幅を恐れて動けなくなるのが一番よくないと思っています。
経営者って、ついブレーキをかけがちなんですよね。
「もうちょっと考えてみたら?」とか「そのやり方で本当にいいの?」とか。
でも、それって社員からしたら、すでに何度も何度も考え抜いた上で持ってきた提案なんですよ。
だから僕は、基本的に「やってみたら?」っていうスタンスです。
うまくいったら万々歳、うまくいかなかったら元に戻せばいいだけ。
社員が何かにチャレンジして会社が本当に潰れるなんてことは、まずないですから。
潰れるとしたら、それは経営者が根本的に判断を誤ったとき。
だからなるべく、社員の「やってみたい」に対しては、前向きに受け入れたいと思ってます。
戻すという選択肢があるなら、失敗してもマイナスにはならない。
成功したら本人も自信になるし、会社としてもプラスになる。
「それ、やってみたら?」これが僕の基本姿勢です。
今も、そしてこれからも「より良い明日」を作るために、会社をどう進めていくかを常に考えていきたいですね。
すでにある幸せに気づくこと。誰かが与える時代はもう終わった
富山の良さはどんなところにあると思いますか?
長岡さん:正直、僕は「富山って、もう十分に幸せな土地だな」と思ってます。
空港があって、新幹線の駅もある。これ、実は全国でも珍しいんですよ。同じ市内にこの2つが揃ってるのって、たぶん福岡の次に近いレベルで、全国でも数えるほどしかない。
けど、富山の人たちって、そのありがたさに気づいてないケースが多い。
やっぱり、外と比べてみることが少ないからだと思うんですよね。
これは日本全体にも言えることで「日本人の幸福度は低い」なんて言われたりしますけど、それって、上ばっかり見てるからじゃないかと思うのですよ。上昇志向が強い分「まだ足りない」「まだダメだ」と感じてしまう。
だからこそ、上を見るなら本気で努力して目指せばいいし、今の幸せを味わいたいなら、下を見て幸福を実感するっていう、どっちかの視点をちゃんと持つべきだと思う。
でもその上で「もっと面白い場所にしたい」と思うなら、自分たちで作ればいい。
それを誰も止めてないし、許可もいらない。
「あの人がやってくれるだろう」と他人任せにしてたら、そりゃつまらんですよ。
僕自身「幸せって何か」と考えると、それは“誰かから与えられるもの”でも“お金持ちになること”でもないと思ってます。でも最近は、SNSでもやたらとお金の話ばかりが出てきて、不安が渦巻いてるような雰囲気も感じます。
SNSで「お金持ちだ」とアピールする人は、どこかで「自分はまだ満たされていない」と感じてるからじゃないかなと思うのです。
お金がないとアイデンティティを保てない、そういう状態だから“お金”という話題に頼ってしまう。
でも、本当に自信のある人って、そこにエネルギーを注がないんですよね。
そう思うと、やはり大事なのは人とちゃんと関わって生きること。
人を幸せにするには、自分が関わるしかない。
関わってない誰かを幸せにすることなんて、基本的にはできないと思ってます。
富山にしても、全国にしても、すでにあるものを活かせてないことがたくさんある。
でも、その火種をちゃんと燃やすか、誰かがブレーキをかけて潰すか。その違いだけで、未来の姿は大きく変わる。
僕は昔から、歴史を調べるのが好きで「なぜこの国はなくなったのか」とか、よく見るんです。
企業の興亡は記録に残らなくても、国の興亡は記録に残る。
例えばユーゴスラビアのように、優秀すぎる指導者のもとで国がまとまっていたとしても、その人がいなくなった途端に崩壊するってこともある。つまり、属人性が高すぎると、その人がいなくなったときに崩れ落ちてしまう。
それは企業も同じことが言えると思っていて。
経営者個人の力に頼りすぎず、再現性のあるチャレンジが自然と生まれる会社であることが重要だと思うんです。だから「次世代がチャレンジできる土壌」を整える責任が経営者にはあると思っています。
そういうチャレンジができる土台が、富山全体としても幸せの連鎖を生むカギになるんじゃないでしょうか。
誰もが主役になれる会社へ。「やってみよう」の輪を、次の世代へ
今後の展望を教えてください。
長岡さん:うちの会社って、急激にドーンと大きくなるようなタイプじゃないんですよ。
だけど、もしこの会社が突然なくなったら困るお客さんがたくさんいる。
だからこそ、替えの効かない存在であり続けること。
それが一番大事なんじゃないかと思ってます。
社員も会社では従業員でも、家に帰ればお父さんであり、お母さんであり、家族にとっての大事な存在です。だから、家庭でも幸せをつくれる人間であってほしいなと。
もし会社が「そんなこと無理やろ」って頭ごなしに否定ばっかりするような場所なら、きっと家でも子どもに「そんなの無理だ」って否定ばかりするようになる。
子どもが「やってみたい!」って言ったら「いいね、やってみたら?」って返せる人になってほしいんですよね。
「やってみよう」っていう言葉、うちの会社の基本方針でもあるんです。
ブレーキをかけない。でも、ただの放置じゃない。
たとえば、子どもがはじめてハシゴを登るときに、危なっかしいけど見守って、後ろからそっとお尻を支える。
そういう“目に見えないサポート”をしながら、登りきったら「すごいね!」って言えるような、そんな関わり方ができたらいいなと思ってます。
そこで「サポートしてやった」なんて言う必要は全くない。
実際、今までの事業もそうやって増えてきたんです。
「それ、やってみよう」「やってみます」っていう一歩が、新しい柱になっていった。
だから、これからも社員一人ひとりが「自分が主役」として挑戦できる会社でありたい。
自分の言葉で、自分の責任で「やってみよう」と言える人が増えたら、世の中もきっともっと面白くなると思ってます。
もちろん、チャレンジには責任も伴います。
「やってみたい」と言った人に「じゃあやってみてよ」って任せる。
それって実は厳しさもあると思うけど、本気になれるし、自分の成長にもつながる。
上の人間が「やってみよう」と後押しをし続けていけば、きっとまた新しい動きが生まれていくはずです。
そうすれば会社の色も、どんどん変わっていくと思うんです。
今いる古参の社員は、これまでの経験もあるし、すぐに切り替えるのは難しいかもしれない。
でも、新しく入ってくる人たちが「やってみよう」の空気に慣れていって、自然と変わっていく部分もある。
そうやって10年、50年、100年と、長く続いていく会社にしたいと思っているのですよ。

背中を押す人になれ。誰かの“やってみたい”を支える側へ
若手世代へのメッセージをお願いします。
長岡さん:人間って、気づいたら誰かの先輩になってるんですよ。
自分ではまだまだだと思っていても、後輩はできている。
だからこそ「やってみよう」って言える大人でいてほしいんです。
もし誰かが悩んでるなら「チャレンジしてみたらいいじゃん」って背中を押せる人になってほしい。
「やっときゃよかった」って後悔するくらいなら、やってみればいい。
もちろん、全部がうまくいくわけじゃないですよ。
でも「あのとき失敗したけど、ここまで来れてよかったな」って思えたら、それはもう成功なんだと思います。
自分では今、会社で一番下だと思ってるかもしれないけど、
下から見上げるばかりじゃなくて、自分の後ろにも目を向けてほしい。
もっと下の世代もちゃんと見てるんです。
「こういう先輩になりたい」って思ってもらえるような存在に、自分がなれたらいいなって。
上の人たちのやっていることって、大きく見えると思います。
でも、いずれは自分たちもその立場になる。
だから、今感じてる「ここは嫌だな」「こうだったらいいのに」っていうことは、
自分の代で変えて、次の世代に引き継いでいってほしいんです。
何か新しいことに踏み出す時って、不安もあるし、勇気もいる。
でもその一歩を踏み出せる環境を、自分たちでつくっていけたら。
それってすごく、素敵なことだと思うんですよね。
“やってみよう。”
それがやっぱり、すべてのはじまりだと思ってます。
ライター:長谷川 泰我