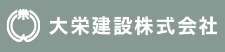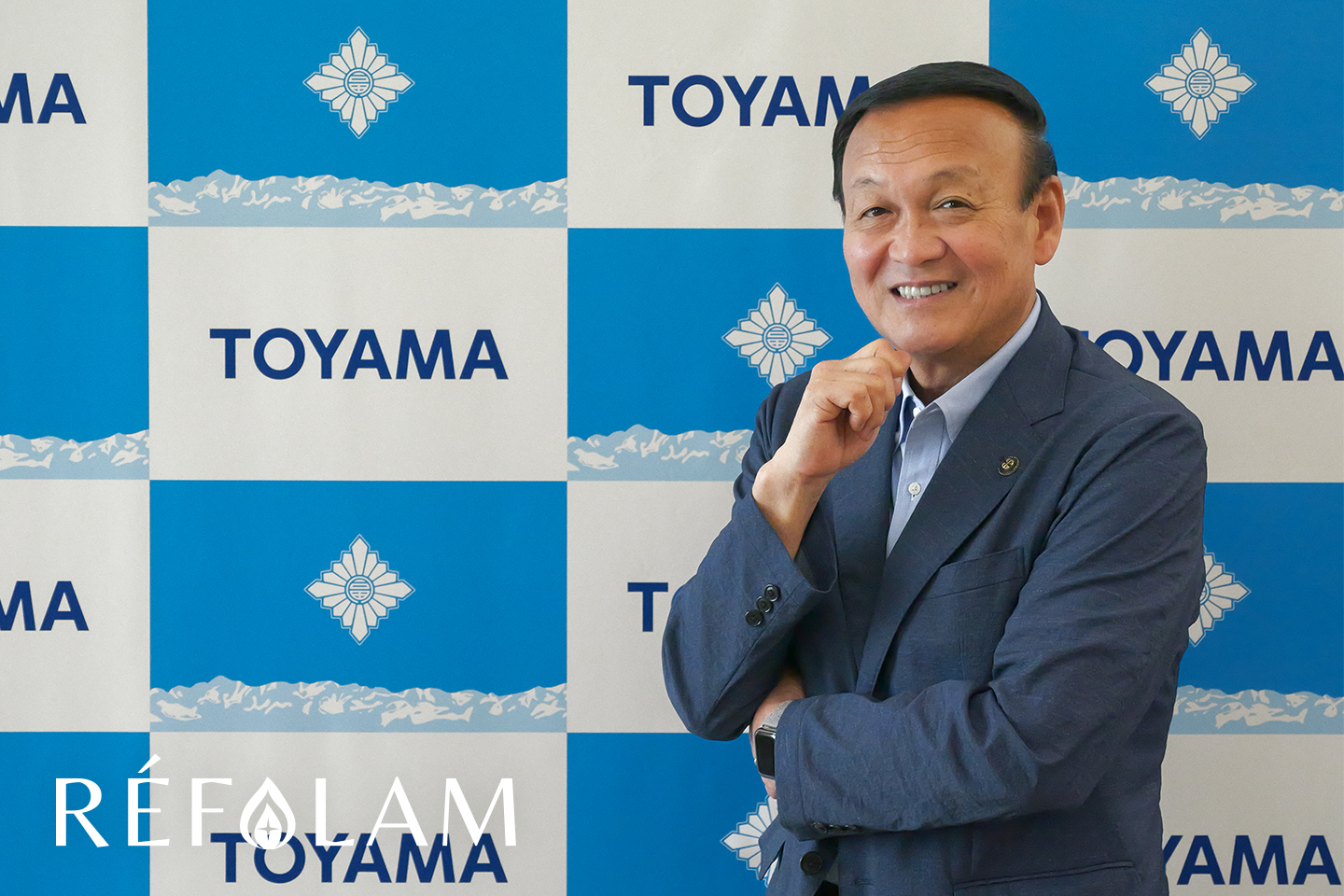「面倒くさい現場、うちに任せてください」手間のかかる工事に向き合う、小さなゼネコンの矜持
まずは、現在の事業について教えていただけますか?
室田さん:うちの会社は総合建設業という形でやっていまして、メインは建築ですね。
その他にも、解体、土木工事、内装、舗装工事なんかも手がけています。
強みって言われると、大手の建設会社をそのまま小型化したような、そんなイメージの建築物を扱ってるって感じですかね。大きな建物は難しいですけど、ある程度の規模ならオールマイティに対応できます。なおかつ、一般的に「面倒くさい」と思われるような、手間のかかる工事を得意としてるっていうのが特徴かもしれません。
お客さんから「あれもしたい、これもしたい」と要望が多くて、その分工程も複雑で、管理も大変になるような現場。そういう“手がかかる”仕事に対して、むしろ前向きに取り組んでいますね。
元々は土木もやってたんですけど、正直、土木の専門業者にはなりきれなかったんですよ。
理由としては、大きな機械を持ってるわけでもなかったし、現場で動く職人さんたちも、昔ながらの「職人」と言えるほど育ちきれていなかった。
時代が進むにつれて、土木の現場もどんどん精巧になっていって、昔みたいな“なんとなく形にする”っていうやり方では通用しなくなってきたんです。
今思えば、そういう流れの中で、自分が得意とする建築の方に自然と舵を切っていったんでしょうね。

家業を継ぐという“当たり前”から、自分のスタイルを探しはじめた。
継承のエピソードを教えてください。
室田さん:うちは祖父も父親も建築に携わっていて、もう物心ついた頃から、家には職人さんがいたり、会社に行ったら「あんちゃん、あんちゃん」って呼ばれたりしてました。
だから、当時はもう「自分が継ぐんやろな」って、特に疑問も持たずに、自然と会社に入ってたというか。ほんとに、ただただ何も考えずにその道を選んだという感じです。
でもね、今の時代なら、もっとフリーに考えても良かったなって思うんですよ。大学出た後に大手の建設会社に就職するとか、富山県内の他の建設会社でもいいから、もう少し世間を見て、勉強してからでもよかったんじゃないかなと。
やっぱり、小さい頃から家業の中にいた分、外の世界を知らずにスタートしてしまったというか、最初のスタートラインがちょっと甘かったのかなと思いますね。
会社を引き継いだ後は、他の会社との付き合いの中で、いろんな社長さんや営業のトップの話を聞いて、「建築ってこういうふうにやっていくもんなんや」って学んでいった形です。
大手のやり方を調べたり、本を読んだりして、建築の世界では「財産を持たない」っていう考え方があるんやなと知って、それに影響を受けた部分もあります。
ちなみに、代表に就任したのは大学卒業してすぐではなくて、しばらく社内で経験を積んでからです。ただ、自分が入社した当時はまだ建設業法とかの法律がそこまで厳しくなくて、業界全体がゆるかったんですよ。
でも、そのうちに世の中全体で法規制が厳しくなってきて、建設業も例外じゃなくなって、法律への対応に追われるようになった。そうなると、自由に会社を伸ばすというよりも、法律に合わせて身を縮めるような感覚になってしまって、そこがやっぱり苦しかったですね。
それでも、なんとかここまでやってきたなと、今はそんなふうに思ってます。

「全員で泥をかぶった」9000万円が消えたあの日と、それを越えて見えた景色。
代表就任後、一番の転機を教えてください。
室田さん:転機という意味では、10年ほど前のある出来事が大きかったです。
高岡のとある小学校で、耐震工事の現場を受けてたんですが、共同で入ってた建設会社さんが、前払金9000万円を受け取ったまま倒産してしまって。
その後、2億円を超える工事の残りを、うち1社で背負うことになったんですよ。
実質1億2000万円で、2億円の工事をやるようなもんで、大赤字。
あのときは本当に会社が潰れるかと思いました。ボーナスなんて出せるはずもない。
でもね、誰一人辞めなかったんですよ。全員がその現場に入って、汗かいて、泥かぶって、何年も必死にやってくれて。
そのとき、銀行の支援もあったし、業界の仲間から「この仕事やってみるか」って助けてもらったこともあって、受注が安定してきた。
で、気づいたら、赤字や黒字のギリギリを行ったり来たりしてた会社が、ある時からスッと上向いて、安定した路線に入ってたんです。
ふと「なんで安定したんやろ」って考えてみたら、やっぱり従業員のおかげやなと。彼らがいなかったら、今の自分の給料もなかったし、会社も残ってなかった。
「企業は人なり」っていう言葉、あるじゃないですか。あれ、ほんとその通りだと思ってます。
求人にしても、やっぱり今の時代、中小企業は大手に勝てん。でも、だからといって最初から完璧な人ばっかり求めててもしょうがない。
育てるしかないんですよ。マイナス費用をかけてでも、人を採って、育てて、いつか元が取れるようにってやらないと。
だから、苦しいときに一緒に頑張ってくれた従業員には、今はもうしっかり還元したいと思ってます。給料も上げたいし、ボーナスも渡したいし、「一緒に分かち合おう」って、ほんとにそういう気持ちですね。
なんか、自分でも花を持たせてるみたいな言い方になっちゃいますけど(笑)
でも、本音です。
自然と暮らしが寄り添うまち、富山。
富山の良さって、どんなところだと思いますか?
室田さん:富山の良さって、やっぱり自然ですね。大学は大阪だったんですけど、向こうに行くと、やっぱり富山の海と立山のあのコントラストが、ふと頭に浮かぶんですよ。
景色が常にそばにあるっていうか、立山がきれいに見えるときなんかは、何気なくてもやっぱり感動しますしね。
それに魚もうまい。仕事に直接は関係ないけど、やっぱり山と海と魚、それが富山の魅力だなって思います。
最近は、全国的に見ても富山の存在感って増してきてるんじゃないですかね。
仕事の数も多いし、それにニューヨークタイムズで「行くべき場所」にも選ばれたりして。
だからこそ、富山全体がもっと盛り上がっていくには何が必要かって考えると、やっぱり「娯楽」じゃないかなと思うんです。
たとえばプロ野球やサッカー、今はバスケもありますけど、ああいうプロスポーツが超一流になって、富山のシンボルとして根付いていくと、まち全体の魅力もグッと上がるんじゃないかと思う。
それで思い出すのが、長崎だったか鹿児島だったか、大企業のスポンサーがバックアップしてサッカークラブを主軸に地域全体を盛り上げた例があって。
スタジアム建てるための資金も出して、運営まで引き受けて、民間が動いたことで街が生き延びたという話。
富山でもそういうモデル、あってもいいんじゃないかなって思うんですよね。
それに今は新幹線もあるから、東京や大阪がそこまで遠く感じなくなってる。
昔は「東京」っていうとすごく遠い存在だったけど、今はもう少し身近に感じられる。
なのに、人の流れは東京ばっかり。私が学生時代に過ごした大阪もどんどん影が薄くなって、文化の発信力とか、もっと頑張ってほしいなって思うときもあります。たとえば紅白歌合戦でも、東京と大阪で交互に開催するとかね。
そうやって西も東も一緒に盛り上がっていくような流れがあれば、日本全体としてのバランスも良くなるんじゃないかなと。
そんなことを、けっこう真面目に思ってたりします(笑)
「自分がいなくても回る会社に」継がせることより、続けられる組織へ。
今後の展望を教えてください。
室田さん:うちの会社は、今「玉田興業」っていう金沢の会社とグループ化しました。
その中でいろいろと模索しながら、一歩ずつ前に進んでるというところです。
そして何よりも「従業員をどう育てるか」ということ。
社内には今、50代前半のメンバーが3人、4人いて、彼らがあと10年は頑張れるように、自分としてもなんとかしてやりたいなと。
でもただ年功序列でスライドさせていくというんじゃなくて、もっと下の世代も巻き込んで、会社として本当に“組織らしい組織”にしていかないといけないと感じてます。
その先にあるのは、「安心してこの会社を任せられる状態」をつくることです。
いつか自分もいなくなるわけですから。だから、自分がいなくても会社が回る、ちゃんと継承されるような形にしておきたい。
ほんとは息子や娘に…と考えたこともありましたけど、やっぱりそこまでの苦労を背負わせるのもどうかなと思って。
せめて、今いる従業員たちが、これからもっと楽に仕事ができるようにしてあげたい。
そんなふうに思うようになりました。
結局ね、これまではどこかで「たくさん稼がせて、たくさんボーナス出したい」っていう気持ちが先に立ってて、肝心な“継承の仕組みづくり”までは手が回ってなかった。
自分が忙しすぎたのもありますけど、やっぱりそこは反省もあります。
もっと社内に、たとえば副社長や部長、課長といった「助言してくれる人」がいればよかったなと感じる場面も多いです。
外には相談できる友人もいますけど、社内にいてくれて、苦楽を共にして時にはブレーキをかけてくれるような存在が、もっと必要だったんじゃないかなと。
だからこそ、これから先は、そういった支え合える体制をしっかりと整えて、会社を“次の世代へ残せる形”にしていきたい。
今は、ただただその一心でやっています。

「まずは、黙ってやってみる」頭より先に、手と足を動かしてみてほしい。
若手世代へのメッセージをお願いします。
室田さん:たいしたことは言えんけど、強いて一言だけ挙げるなら「チャレンジ精神」やと思います。
悪く言えば“殴り込みチャレンジ”ですけどね(笑)。
とにかく、やる前からあれこれ文句を言わずに、まずはやってみること。
経験者に「こうやってみ」と言われたら、とにかくその通りに、素直にやってみる。
それが一番やと思ってます。
うちらの業界で言えば、泥だらけになってもええんですよ。
毎日毎日、言われたことを黙って一生懸命やっていく中で、だんだんと見えてくるもんがある。
その中から、初めて「自分はこうしたい」とか「ここが嫌や」っていう文句も出てくるし、次の目標も見えてくる。
何もせんうちから頭でっかちにならんと、まずは体を動かしてみる。
そういう姿勢でいてほしいですね。
まずは、やってみる。それがすべてのはじまりやと思います。
ライター:長谷川 泰我