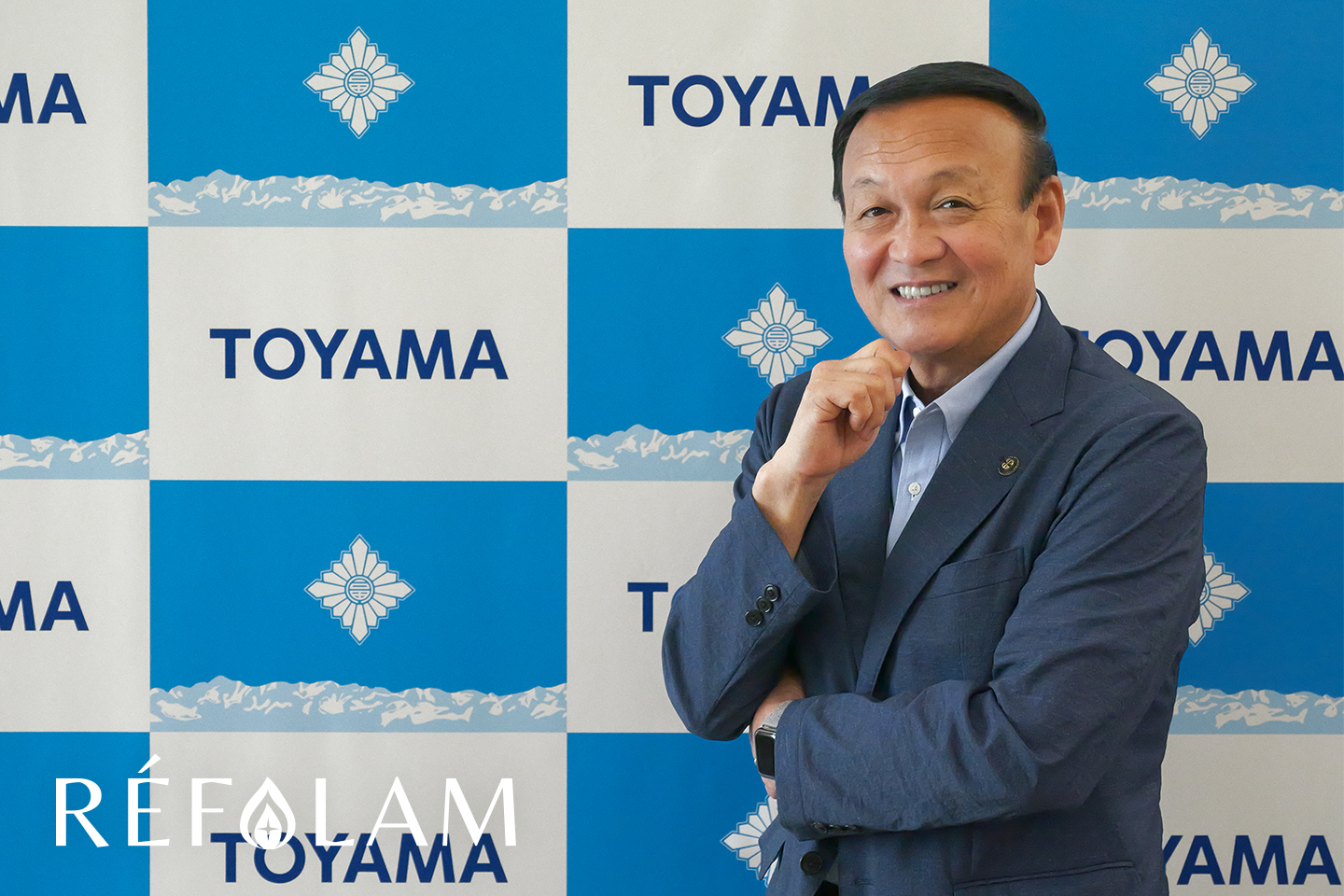縁の下の力持ちとして、インフラと地域の未来を支えるしごと。
まずは、現在の事業について教えていただけますか?
遠藤さん:主な事業は、セメント関連の建設工事と、電力会社さんの火力発電所などでのプラント設備の工事、それから空調設備の清掃、さらにフライアッシュのリサイクル事業。
そして最近始めた新しい柱として「スポーツマネジメント事業」が加わりました。今はこの5つを軸に仕事をしています。
中でも主力になっているのは、セメント関連のコンクリート補修の仕事。
建物や橋などのインフラって、もう新しく建てる時代じゃなくて、今あるものをどう延命するかっていう時代に入ってきてるんですよ。特に、高度成長期に作られたコンクリート構造物なんかは50年以上経ってて、あちこち劣化してる。
それを壊して建て直すんじゃなくて、限られた予算の中で補修しながら使っていく。そのニーズがこれからも高まってくると思っています。
弊社では「当たり前の生活を支える縁の下の力持ちであろう」という想いを掲げていて、例えば電気を安定して供給するために必要な設備の一部を我々が担ってるとか、空調の仕事だったら建物の中の空気をきれいに保つ役割をしているとか。
表には出ないけど、社会のインフラを裏側から支えている。そんな自負を持って仕事しています。
生活インフラに関わる事業は「当たり前を守る」仕事。そこに加えて、スポーツ事業を通じて「まちに新しい価値を加える」こともできるんじゃないか。
そんな想いで今、インフラとスポーツの両輪で会社を動かしています。

富山交易の歴史と、変化の道筋。
御社の歴史について教えてください。
遠藤さん:うちは今年で創業78年になります。もともとは旧三菱商事の富山支店としてスタートしましたが、戦後の財閥解体のタイミングで「三菱商事として残るか、それとも独立するか」という選択が迫られた中で、「富山交易」という名で独立する道を選んだ、というのがはじまりです。
創業者は私の曾祖父にあたります。そこから長い年月をかけて、機械の販売、セメントの取り扱い、ガソリンスタンドの運営、スプリットブロックの製造など、時代ごとにさまざまな事業を展開してきました。私は6年前に代表取締役に就任し、代としては5代目にあたります。
正直なところ、以前は「富山交易といえば、生コンと石油スタンドの会社だよね」と言われることが多かったです。でも、今はどちらの事業も当時とは大きく形を変えています。
たとえば、生コンは今も取り扱っていますが、自社製造ではなく、組合に属して仕入れて販売している形です。ガソリンスタンドもすでに運営していません。
つまり、かつての「顔」だった2つの事業がなくなった今、「富山交易って何の会社?」と聞かれることも少なくありません。だからこそ「自分たちは何によって社会に価値を提供していくのか」を常に問い直しているところです。
そうした中で、新たな挑戦の一つとして立ち上げたのが、スポーツマネジメント事業です。まだ発展途上ではありますが、「富山交易といえばサッカー」という新たなイメージが少しずつ広がってきているのも事実です。事業の枠を超えて地域とつながる試みとして、これからさらに育てていきたいと思っています。
でも、この会社は決して私の“所有物”ではありません。継承していくにしても、血縁にこだわる必要もない。リーダーとしての資質がある人が、社内外問わず担ってくれればいい。
社員から社長が生まれたって、まったく構わない。
誰もが「自分のやりたいこと」に挑戦できる、そんな組織にしていきたいと思っています。

母の死をきっかけに変わった価値観。
だからこそ、チャレンジできる会社にしたい。
価値観が変わった瞬間はありましたか?
遠藤さん:正直、若い頃は仕事や人生について、真剣に考えたことなんてなかったんです。大学時代も遊びが中心で、「自分が何をしたいのか」なんて、まったく見えていなかった。
でも、ある出来事が、その考え方を一変させたんですよ。
私が42か43歳の頃のこと。母がバレンタインの日に突然倒れて、翌日にはこの世を去ったんです。
ちょうど倒れる一年前に、「脳の血管に少し問題はあるけど、こんだけ長く生きてれば手術はいらない」って医者には言われていて、まさかそんなことになるとは想像もしていませんでした。
そのときに、「人って、本当にあっけなく死ぬんだな」と思ったんです。自分も、いつ何があるかわからない。だったら、やりたいことをやっておかないと。強く、そう思うようになりました。
悔いのない人生を生きたいと、心から思ったんです。
そのとき、自分のこれまでを振り返って、「自分がお世話になってきたものは何だっただろう」と考えました。
真っ先に浮かんだのが、やっぱり“サッカー”でした。子どもの頃からずっと夢中になって、仕事でも、人脈でも、結局はサッカーから得たものが一番多かった。
だったら、自分にたくさんの事を与えてくれたサッカーに、なにか恩返しができないだろうか。そう考えるうちに、「スポーツを通じて地域を元気にしたい」というビジョンが、自然と生まれてきたんです。
所詮、人間は誰しも死ぬときは一緒。どんなに偉い人でも、最後は平等です。
私はサッカーを通じて、たくさんのスター選手と出会ってきましたが、みんな本当に謙虚で、驕らず、だからこそ尊敬できた。その姿勢を見て、私自身もそうありたいと思いましたね。
だから社員にも常々伝えています。「悔いのない人生を送ってほしい」と。
だからこそ、「仲間を大事にすること」「実現のためにどうするか考えようよ」この2つを会社の文化として大切にしているんです。
実際、社員のみんなもわかってきてくれていると感じてますね。「できません」ではなく「どうすればできるか」を考えるようになってくれている。
それが、何より嬉しいですね。
だから、若い人たちにも、もっともっと挑戦してほしいと思っています。
やりたいことって、大抵は新しいことですから、失敗する可能性だって高い。でも、だからこそやる意味がある。私は失敗した人間をちゃんと評価したい。
1勝9敗でもいい。その1勝が、未来を変えるかもしれないんです。
私たちが今取り組んでいる「まちなかスタジアム構想」も、できるだけ若い人たちが主体になって動けるプロジェクトにしたいと思っています。富山の人たちでつくっていく。それが理想です。
年長者が若者のチャンスを奪うような社会にはしたくない。そう強く思っています。
人生は、いつ終わるかわかりません。だからこそ、せめて「遠藤がいなくなって寂しいな」と思ってもらえるような人間でありたい。
楽しく生きて、「楽しかった」と言って死ねるような、そんな人生を歩みたいんです。
だから今、挑戦し続けています。それだけなんです。

200通の本音に打ちのめされた日から、すべてが変わった。
大変だったエピソードをお聞かせください。
遠藤さん:大変だったことっていわれると…難しいけど(笑)
社長になって3〜4年目くらいの頃、社内アンケートを実施したことがありました。
第三者に依頼して、社員全員に匿名で、自由に本音を書いてもらう形式でお願いしたんです。
「遠慮せずに、正直に書いてほしい」と。
返ってきたのは、200件を超える回答でした。
それを読めば読むほど、胸にグサグサ刺さるような内容ばかりで…。
「社長が暴走している」とか、「理想ばかりで現実が見えていない」とか、「重たい」とか。
喫茶店にこもって、5時間くらい一人でずっと読み返していました。
何杯コーヒーを飲んだか、もう覚えていないくらいです(笑)。
正直に言うと、めちゃくちゃ落ち込みましね。
もちろん、中には励ましの言葉もありましたが、8割近くは厳しい内容だったと思います。
それでも、すべての声をしっかり受け止めて、役員たちとも共有し、「これからどう変わっていくべきか」を本気で話し合いました。
あのアンケートは、今振り返っても「もう二度とやりたくない」と思うくらいしんどい経験でしたが、
同時に、自分にとってすごく大きな学びにもなったと思っています。
自分の未熟さを正面から受け入れるしかなかったし、「リーダーとして何が足りていないのか」を真剣に考えるきっかけになりました。
そんなとき、高校時代からの友人でもあり、経営者仲間の方にこう言われたんです。
「お前、社員には“失敗してもいい”って言ってるんだろ? だったら、まずお前が失敗してみろよ」って。
その言葉にハッとしました。たしかにその通りだ、と。
それから少しずつ、自分の考え方が変わっていきました。
「失敗してもいい」と言いながら、実は自分がいちばん失敗を恐れていた。
でも、社長である自分こそが率先してチャレンジし、そして失敗したときにはちゃんと謝る。
そうやって姿勢を見せることが、社員の挑戦を後押しすることにつながるんじゃないかと考えるようになったんです。
「失敗しちゃいけない」という空気を、少しでも会社の中から減らしていきたい。
そんなふうに思うようになりました。
今取り組んでいるスポーツマネジメント事業も、正直どうなるかなんて全くわかりません。
でも、だからこそ、やる意味があると思っています。
未来のことは誰にもわからないし、確実な成功法則なんて存在しない。
だったら、自分を信じて進むしかない。今はそう思っています。
あのときの経験と、かけてもらった言葉には、今でも本当に感謝しています。

富山がもっと面白くなるために。チャンスと個性を尊重する県であってほしい。
富山がより良くなるためには何が必要だと思いますか?
遠藤さん:富山がもっと面白くなるためには、やっぱり「みんなにチャンスがある県」になっていくことが大切なんじゃないかと思っています。若い人から年配の方まで、誰もがいろんなことにチャレンジできて、それを受け入れてもらえる空気がある。
それが大事なんじゃないかなと。
具体的には、「やりたいことを自由に言えて、形にしていける環境」があることですね。
もちろん、全部が全部うまくいくわけじゃないし、精査は必要です。でも、「やってみたい」と思ったときに、「じゃあ一緒にやろうぜ」って言ってくれる人がいる。
それが富山の中で当たり前になったら、きっともっと面白くなると思うんです。
私は「富山から出ていくな」とは言いません。外に出てもいい。でも、いつかその人たちが育った富山に対して何かしら還元できる機会があれば嬉しい。そのときに、富山にちゃんと“場”があること。
挑戦できるフィールドがあること。それが大切だと思っています。
ただ現状としては、まだもうちょっといけるんじゃないか、と感じているのも事実です。
ものすごくオブラートに包んで言えば、「もっと個性を活かせる県になってほしい」と思っています。
「前例がないからダメ」「富山では実績がないから無理」といった言葉を、正直よく耳にします。
でも、新しいことに“実績”なんてあるわけがないんですよ。他県ではやってるのに、富山では前例がないから…って言われたら、そりゃ若い人たちも窮屈になりますよね。
そういう意味でも、私は「個性をもっと尊重できる県になってほしい」と思っていますし、それを実現するには、「主体性」がキーワードだと思っています。
自分の意思で動く、自分のやりたいことに挑戦する。それが「楽しい」と感じる原動力になるんです。
そして、その裏には「失敗してもいい」と言ってあげられる環境が必要です。
挑戦を支えるのは、“成功の保証”ではなく、“失敗しても支えてもらえるという安心感”だと思っています。だからこそ、そんな富山になっていってくれたら、民間も行政も、もっと元気になるんじゃないかと感じています。
“楽しい会社”をつくる。正解のない経営に、信頼と挑戦で向き合っていく。
今後の展望をお願いします。
遠藤さん:究極的には、「楽しい会社にすること」。私は、そこに尽きると思っています。
弊社の企業理念は「社会に期待と信頼を提供して貢献する」というものですが、その実現のためには、まず関わってくださるすべての人に「この会社、なんか面白そうだな」「楽しそうだな」と思ってもらえる存在になることが大切だと考えています。
だからこそ私は、会社の雰囲気づくりにとことんこだわりたいと思っているんです。
そのためには、社員との信頼関係が欠かせません。
私が「失敗してもいい」と言っているのに、実際に社員が失敗したときに怒ってしまったら、それは全然違う話になってしまいますよね。
だから私は、どんなときでも「よくやった。今回は残念だったけど、次また頑張ろう」と言えるような関係性を築いていきたいんです。
日常的なコミュニケーションもとても大切にしています。
一緒にご飯に行ったり、ちょっとした会話の中で本音を引き出したり。そうやって、お互いに「ちゃんと向き合ってくれているな」と感じられる関係を、社内はもちろん、お客様や協力業者の皆さんとも育んでいきたいと考えています。
そして、結果というのはすぐに出るものではないので、社員にも言うんです。
「すぐに結果を求めるな」と。
「やってみたい」と思ったことに、結果が出るかどうかなんて誰にもわかりません。
でも、だからこそ挑戦する意味がある。そこに価値があると思っています。
新しいことにチャレンジして、その中で「どこで引き際を決めるか」を考えていけばいい。
失敗も含めて全部を肯定していける、そんな会社でありたいと願っています。
「言われたことだけをやる」会社になってしまったら、きっと誰にとっても楽しくないし、長続きもしません。
だからこそ、「面白そうだからやってみよう」「自分がやってみたいから挑戦する」そんな主体性が自然と生まれる環境をつくっていきたいと思っています。
うちは大企業ではないからこそ、フットワークの軽さがあります。
「面白そうだね。じゃあ、明日からやってみよう」そんなスピード感で挑戦できる会社でありたいんです。
結局、経営に“正解”なんて存在しないと思っています。
私自身、今やっていることが正しいかどうかなんて、10年後にならないとわからない。
でも、それでいい。
少なくとも、人を不幸にしない方向で進んでいるのであれば、それが“自分たちなりの正解”なんじゃないかと、今はそう思っています。

チャレンジ最高!失敗ウェルカム
若手世代へのメッセージをお願いします。
遠藤さん:若い人たちに伝えたいことは、たった一つです。
「どんどん失敗してください」
もう、これに尽きます。チャレンジせずに無難に生きていては、新しいことなんて絶対に生まれません。挑戦した結果、失敗したとしても、それが次への糧になります。
1発1中なんてものはありません。私は「1勝9敗でいい」と常々言っていますが、9回の失敗の中に、たった1回の“本物”が隠れている。そう信じています。
ただ、失敗して「あーだめだった」で終わらせてはいけません。
そこから「なにを学んだのか」「次にどう活かすのか」をちゃんと考える。失敗の中にあるヒントを、自分なりに見つけて、次に生かす。
その繰り返しで、少しずつ前に進んでいけばいいんです。
私は、そうやって挑戦している人を心から応援したいと思っています。苦しい時もあるかもしれませんが、そのプロセスがあってこそ、本当に意味のある一歩になるはずです。
だから、とにかく恐れずにチャレンジして、思いっきり失敗してください。
そこから始まる未来を、私は楽しみにしています。
ライター:長谷川 泰我