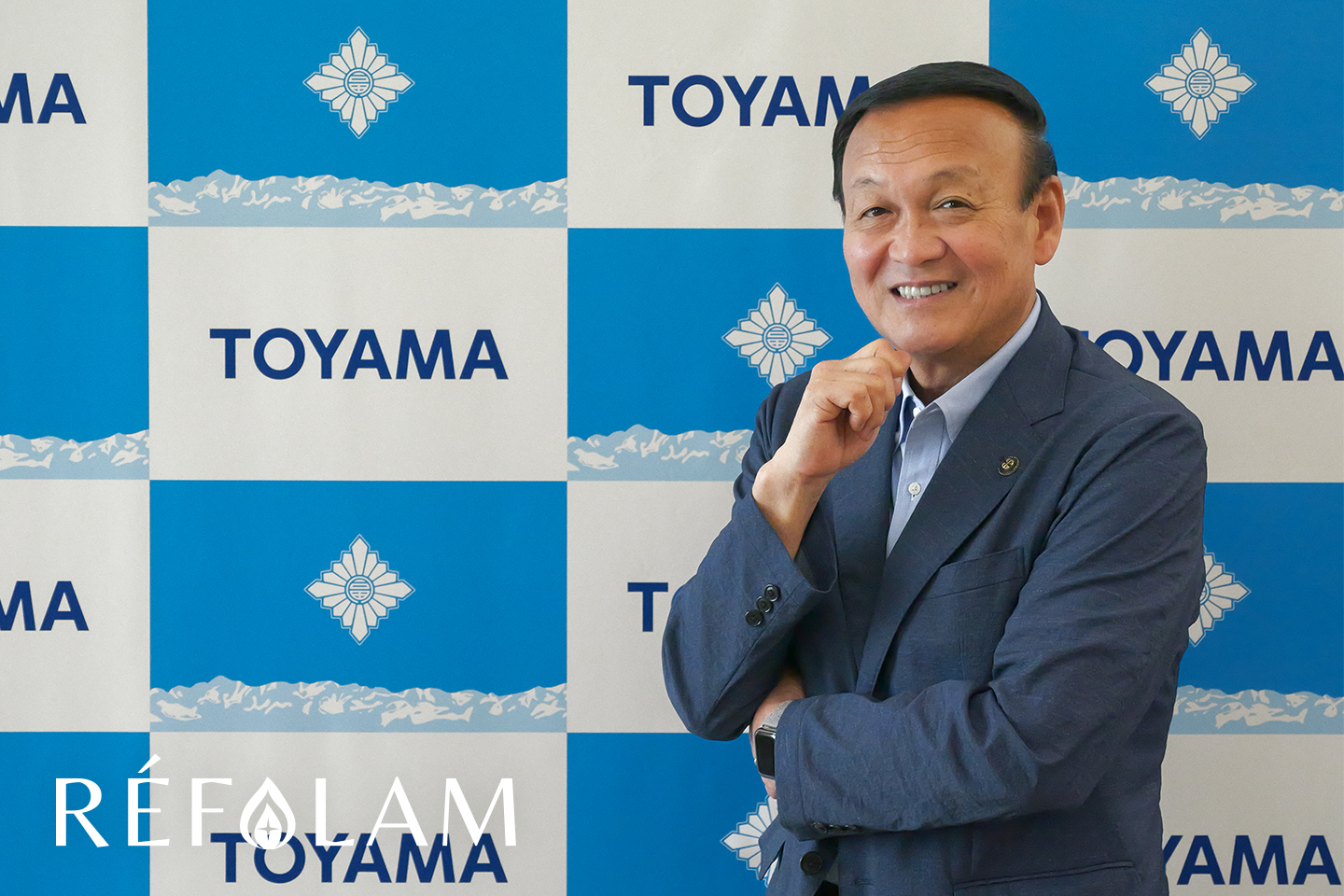RÉFLAM Special movie.
世界を魅了した醸造家が、富山で日本酒を造る。
事業開始の背景を教えてください。
シャルル氏:私は長い間、LVMHグループのMoët Hennessyで世界中のマーケットを担当してきました。アジア、アメリカ、数え切れない都市を回り、何千本ものシャンパンを売ってきた日々。
その私が、2018年、Dom Pérignon の醸造最高責任者だったリシャールから「富山で日本酒を造らないか」と声を掛けられた瞬間、心が大きく揺れ動きました。
日本酒はここ30年、右肩下がりの市場。
私はもともと日本酒が好きで、多くをコレクションしていたのですが、この状況にどこかもどかしさを感じていました。
「伝統に敬意を払った上で、角度を変えれば、この酒はもっと輝けるのでは。」
数多くの日本酒を愛してきた経験が、その直感を裏付けていました。
リシャールの誘いは、まさに‟adventure”挑戦の始まりでした。

アッサンブラージュで「調和の美」を再定義する
IWAの特徴を教えてください。
シャルル氏:IWAの象徴的な技術、それがアッサンブラージュです。
複数の酒米、酵母、酛からなる原酒をブレンドし、複雑かつ奥行きのある味わいを創り出す手法は、シャンパーニュの世界では当たり前でも、日本酒では前例がありませんでした。
毎年異なる表情を見せるIWAは、「完成形」をつくらない酒です。
その年、その瞬間における最良を探り続ける。
その哲学が、IWAをただの日本酒ではない“文化的体験”へと押し上げています。
IWAを口にした人々が口を揃えて言うのは「どんな料理にもマッチする」という驚きです。
フレンチ、中華、和食、肉料理、そしてフランス人として大きい声では言いづらいですが、フランスチーズとの親和性は完璧です。
ペアリングの可能性は、既存の枠を超えて広がっていると思っています。

富山というロケーション、それ以上の意味とは
なぜ富山という地を選んだのでしょうか?
シャルル氏:IWAが富山・白岩の地で生まれたのは、偶然ではありません。
雪解け水が流れ、冷涼な気候が育む自然。
そして何より、地元の人々の故郷への誇りと情熱。いわゆる「富山プライド」です。
彼らの誠実さ、土地への深い愛情が、このブランドのDNAとなっています。
酒米づくりから仕込み、熟成までを一貫して行う白岩の蔵は、世界的建築家・隈研吾氏が設計しています。ここでは木材や和紙などをはじめとした地元の素材を活かし、伝統と革新が調和した空間は、訪れる者すべてを魅了すると確信しています。
そして地元の人々の富山プライドが私たちを支え、ブランドの魂として深く刻まれています。
白岩の心が富山にあること。
それがIWAの何よりの力です。

グローバル市場への挑戦
立ち上げた後に最も苦労した体験を教えてください。
シャルル氏:IWAを立ち上げた当初、私は「このブランドは必ず世界で受け入れられる」という確信と自信を持っていました。
その理由は、私たちが長年培ってきたシャンパーニュの歴史が教えてくれています。
かつて日本ではシャンパーニュは特別な場だけの酒でしたが、今やどこでも手にすることができ、多くの人に当たり前のように楽しまれています。
日本酒も同じように、国境を越え、日本の文化として世界に浸透する未来を描けると信じています。
ただ、意外だったのはフランス市場の難しさでした。
地元ワインへの信頼が絶対的なフランスでは、日本酒を受け入れてもらうのは当初想像していたよりも簡単ではありませんでした。
だからこそ、私たちはパリのトップシェフたちと手を組み、ワインペアリングのコースの中にIWAを組み込んでもらうアプローチを選びました。
その結果、ゆっくりとですが、IWAは世界の高級レストランやコレクターの間で存在感を高めています。

日本酒を超えるブランドへ
今後の展望を教えてください。
シャルル氏:IWAの挑戦は、日本酒造りにとどまりません。
白岩の蔵を世界中のファンを惹きつける“富山の玄関口”となるようなブランドを創造したいです。
つまり、無農薬の酒米栽培や蔵見学の体験はもちろん、富山の自然や食、文化を五感で味わえる拠点としての価値を高めていきたい。
最近ではニューヨークタイムズでも特集されましたが、海外で富山を知る人はまだ多くはありません。
しかし、蔵や立山の写真、景色の美しさを見せると、誰もが「行きたい」と目を輝かせるのです。
その反応を確信に変え、私たちは「富山から世界へ」という旗を掲げ続けています。
IWAは富山の自然と誇りを背負いながら、世界に向けた“Made in Toyama”のブランド体験を創り上げて、この地に訪れるきっかけとなります。
そして、単なる酒蔵だけではなく、富山という地域そのものの象徴となっていきたいですね。

日本酒の常識を覆す、富山発の挑戦。
若手世代へのメッセージをお願いします。
シャルル氏:日本酒には、どこか“古い”“堅い”というイメージが残っているかもしれません。
居酒屋で飲むもの、年配の方が好むもの、そんな固定観念があるかもしれません。
ですが、IWAはそのイメージを覆す力を持っています。
私たちが目指したのは、日本酒の枠を超えた体験です。
伝統的な製法を尊重しながら、ブレンドの発想を取り入れ、食のシーンを限定しない柔軟さを追求しました。
だからこそ、カジュアルな食卓でも、記念日のテーブルでも、あるいは世界中の名店でも、自然に寄り添うことができるのです。
若い世代の方々には、ぜひ一度IWAを試していただきたい。きっと、いい意味で驚くはずです。「これが日本酒なのか」と、新しい発見を感じてもらえると思います。
富山・白岩で生まれたIWAは、今もなお進化を続けています。
次の世代とともに、新しい文化としての日本酒を育てていけたら。
それが、私たちの願いです。

ライター/撮影・編集:長谷川 泰我