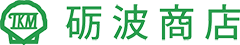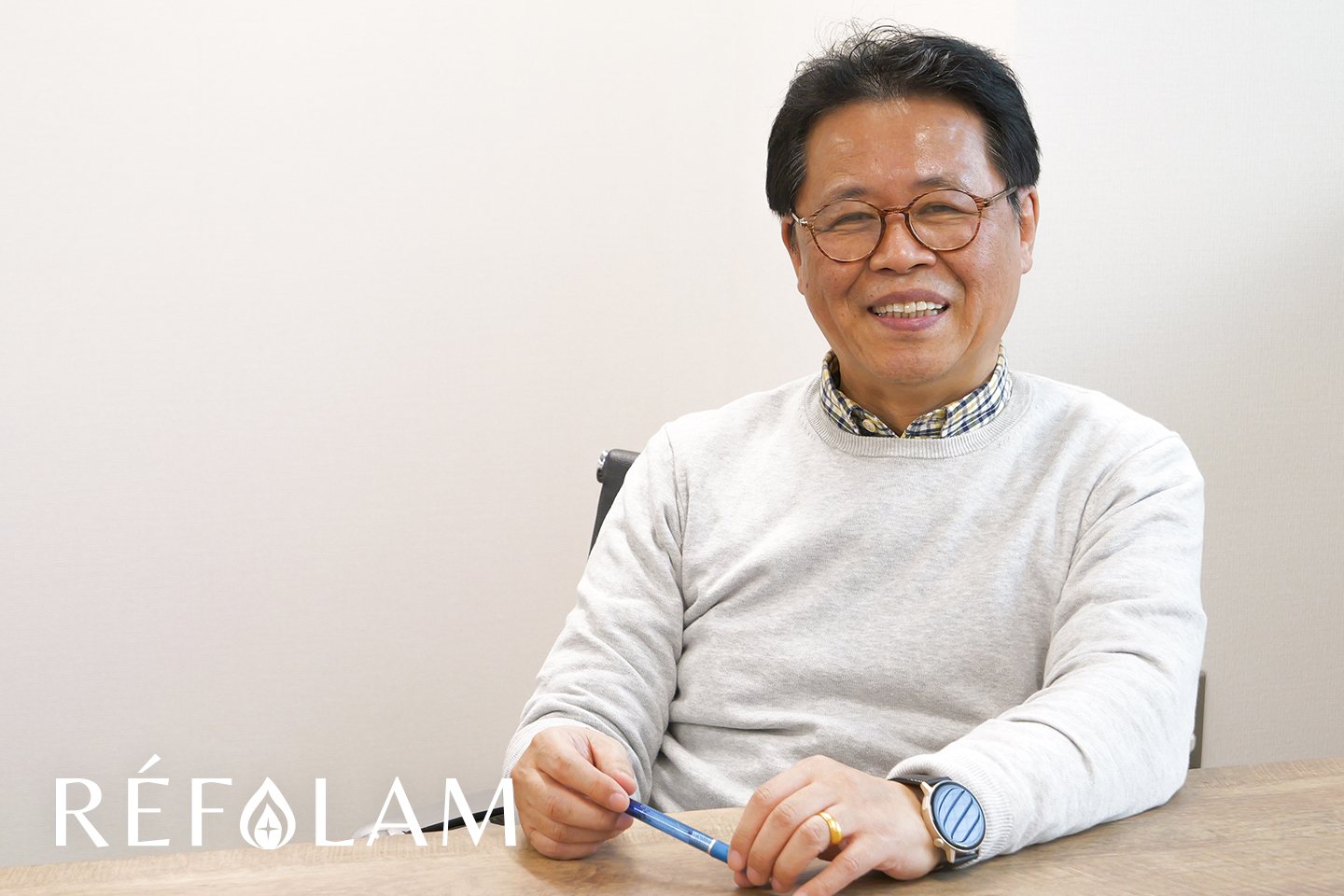事業内容について教えてください。
砺波さん:弊社は、旅館や飲食店などの業務用市場に向けて、アルミ製の食器を中心とした金属製品を企画・卸販売する会社です。
製造自体は高岡市内の職人ネットワークと連携しながら進めており、長年の経験と品質へのこだわりを武器に、特注対応にも力を入れています。
もともと弊社は、戦後まもなく祖父が始めたバケツ・ヤカンの卸業からスタートしました。
時代の変化とともに、現在はアルミ鋳造製品に事業の軸を移し「陶器のような美しさと、割れにくさを兼ね備えた器」という独自の製品開発を続けています。
背景には、高岡という町のものづくり文化があります。
高岡市は江戸時代初期、前田利長公が金沢から鋳物職人を招き、町ごとゼロから開いた歴史を持つ土地です。その流れをくむ高岡銅器の技術が、今もなお鋳造のまち・高岡を支えています。
弊社の商品も、そうした地域の技術に支えられながら、全国の料理人や宿泊業の皆さまに“割れない美しい器”として選ばれるよう、日々活動しております。

陶器に見えて、割れない。唯一無二の技術が生まれた理由
どのようなきっかけで製品が生まれたんですか?
砺波さん:ぱっと見、これ「アルミのコップなんです」って言っても、たぶん誰も信じないと思うんですよ。見た目は完全に陶器なんです。
でも、これが全部アルミでできてるんです。
こういう塗装ができるのは、たぶん日本で弊社だけじゃないかなと思います。
実際、ここに並んでる器全部アルミなんです。陶器みたいに見えるけど、落としても割れない。驚かれる方が多いです。こんなことができるのは、塗装屋の職人さんが、ずっとそればっかりやってきてくれたから。
技術的には、他の会社さんでも10~20年ぐらいかけて研究すれば、できないことはないと思うんです。
うちは、それを愚直に積み重ねてきたってだけなんですよ。
まさに職人技ですね。
元々は、黒色の鍋や釜みたいな、いわゆる単一色の商品をずっと作っていたんです。
でも、それは技術的に難しいわけではなく、海外で安く生産されて、日本に入ってくるようになりました。うちはずっと国内生産にこだわってるんですけど、当時は価格で完全に負けてたんですよね。
それで「じゃあ、どうやって差別化していくのか?」と考えたときに、海外では真似できないことをやるしかないと。
そのとき、お付き合いのあった問屋さんから「陶器って割れるじゃないですか。だったら、陶器のように見えて、でも割れない器を作ってみたら?アルミだったら割れないでしょ?」って提案されたんです。これが、すべての始まりでした。
その問屋さんっていうのが、旅館や飲食店をよく回っていらっしゃる方で。
現場のリアルな声を聞いて、それをちゃんとメーカーにフィードバックしてくれる柔軟な発想の持ち主だったんです。その方が、うちのことを気に入ってくださって「こういう声、けっこうあるよ。やれるならやってみなよ」って言ってくれた。
正直、それがうまくいくかなんてわからなかった。
でも、当時のままの商売を続けていてもダメなのは明らかだったから、とにかくやってみたんです。
言われた通りにやって、ダメ出しされて、また直して……っていうのを繰り返して、ようやく今の形になった。
それが、いまではうちの強みであり、うちの製品の価値として、お客さまに選んでいただけてる理由になってると思います。
ある意味、運命的な出会いでしたけど、それもやっぱり、お客さまの声に耳を傾けて、無下にせずに愚直にやり続けてきたからこそ、今があると思います。
改めて「お客さまの意見に真摯に向き合うこと」が大事なんだなと実感しています。

誰も知らない“すごいもの”を伝えたい。高岡の技術とともに
仕事への想いを教えてください。
砺波さん:僕自身、一度県外に出てから戻ってきた人間なので、余計に思うんですけど……うちの商品、ほんとにすごいと思うんです。自分では作れないですからね。それぐらい技術的に高度なものなんですよ。
でも、それを旅館さんとか飲食店の方々って、ほとんど知らないんです。全くといっていいほど。
営業で持って行って「え、なにこれ?めっちゃいいじゃん!」って2人に1人くらいは言ってくださって。
でも、それまでは誰もその存在を知らない。
それって、すごくもったいないなと思っていて。
結局これは、高岡銅器の職人さんたちが積み上げてきた技術の結晶なんです。
だから、僕自身の仕事としては、単に売上を上げていくっていう以上に「これは高岡銅器の技術なんです」ってことも一緒に発信していけたら、高岡という町そのものがもっと着目されて「あの町ってすごい技術持ってるよね」って思ってもらえるんじゃないかって。
それが一番の想いですね。
高岡の現場には、今も職人さんがいっぱいいるんです。
でも、収益減少や事業継承の問題で、どんどん減ってきてる。
続けてても儲からない。だったら、儲かるようにすればいいし、仕事があるようにすればいい。
それって結局、営業側の工夫や力不足のせいだと思ってるんですよ。もっと見せ方を変えたり、工夫して売れる商品にしたり、新しい切り口を作っていく。
高岡の中にも、やろうとしてる人はいるけど、なかなか結果が出ない。私自身もそうですが。そこが歯がゆいですね。
どう打開するかって、正直まだ答えは見えてないです。
でも1つ言えるのは「やり続けること」じゃないかなと。以前、ある方が言ってた話が印象的で。
波佐見焼ってありますよね。今では人気ですけど、最初は「なんだこれ、安っぽい」って馬鹿にされてたそうです。
それが30年、40年かけて、ようやく評価されてきた。
つまり、何がいつ火を吹くかなんて分からない。
だからこそ、やり続けて、発信し続けることが大事なんですよね。
もちろん時代に合わせて、総合商社みたいに時流に合わせた商品を取り揃えていくのも1つのやり方だと思います。でもそれとは逆に「1つのことをとにかくやり続ける」っていう姿勢もありだと思ってて。
うちはたぶん後者。だから、いつか評価される日が来ると信じて、自分たちの価値を伝え続ける。
その繰り返しです。
もしかしたら、明日ヒットするかもしれないし、1年後か10年後かもしれない。
でも、続けないことには、絶対に当たらない。そういう想いで、いつも営業に行ってます。

職人の技を、もっと世界へ。まずは“売れる”きっかけをつくる
今後の展望を教えてください。
砺波さん:うちの今後の展望としては“いいもの”を、もっと国内はもちろん、海外にも発信していきたいという想いがあります。
そのためには、まず求められたときに、すぐに提供できるように生産体制の安定が必要だと感じています。現在は、高岡のものづくりのネットワークに支えられながら製造を行っていて、鋳造・加工・塗装といった工程を、それぞれの専門職人さんたちと連携して進めています。
ただ、それぞれの工場さんも職人の高齢化や機械の老朽化で、生産量が増えていきません。
そのため、自社としてもできることを増やしていくことが今後のテーマです。
自社でできる工程を増やせば、生産のリードタイムも安定しやすくなります。お客さまからの「こういうもの作れますか?」という声に、より柔軟に応えられる体制が整っていくと思っています。
とはいえ、そういった体制を築くには、やはり“きっかけ”となるような商品が必要です。
ヒット商品がひとつでも生まれれば、自然と受注も増え、生産体制も拡充していく流れが生まれてくる。
だからこそ、まずはお客さまに届く魅力的な商品づくりに力を注ぎたいと考えています。
ただ、その“ヒットの種”がどこにあるかは、簡単にはわかりません。私自身いろんな本を読む中で印象に残っているのは「アイデアは突然降ってくるものではなく、日々の課題意識や経験の中から自然と生まれるものだ」という言葉です。 だからこそ、止まらずに動き続けること、情報を集め、試し、また考えること。
トライアンドエラーを繰り返す中で、自分なりの答えが見つかると信じています。

興味があるなら、まず3年。答えはその先で見えてくる
若者へのメッセージをお願いします。
砺波さん:富山にいる若い人たちに対して「外に出るな」って言うつもりはまったくないんです。
むしろ、外を見て、他の場所で経験を積んで「ああ、ここがいいな」って思ったらそこに生きていくのも全然ありだと思います。
で、その上でまた富山に戻ってきたら、きっと違った角度からこの土地の良さが見えてくることもあると思うんです。
だから、私が伝えたいのは
「自分が今、少しでも“楽しい”とか“面白い”とか“興味ある”って思えることを、まずは最低3年間やってみてほしい」ってことですね。
やってみないと、わからないことってたくさんあるじゃないですか。
で、その“やってみた3年間”のなかで、夢とか目標とか、将来の展望っていうものの、なんとなく輪郭が見えてくる。
そしたら、そのときに初めて、自分の就職先とか、どんな人生を歩んでいきたいかっていうのを、ゆっくり考えてみたらいいと思うんです。
今は、転職が当たり前になってきてますけど……正直、1年じゃ何もわからない。
3年経っても、本当のところはわからないかもしれない。でも、それでも、やっぱり「続けてみる」「飛び込んでみる」っていうことが大事なんじゃないかと思います。
もちろん、嫌なこともあるし、理不尽なこともある。それでもなお、自分の意思でやってみた経験って、あとから必ず意味を持ってくる。
だからこそ、最初からあれこれ決めつけすぎずに、まずは飛び込んでみる。
その先で、きっと何かが見えてくるはずです。
ライター:長谷川 泰我